投資は教育資金を貯めるのに向いてない?!

お金が必要な時=儲かっている時とは限らない
実は、投資は教育資金を貯めるのには向いていないと言われています。
その理由は・・・?
投資というのは、どんな種類のものでも引き出すタイミングというのが重要です。
例えば、1株1000円で買った株を、900円に値下がりしたタイミングで引き出す人はいませんよね。(損切りを除く。)
1株1100円に値上がりした時に引き出して儲けを出すというのが、投資の目的ですから。
そんな引き出すタイミングが重要な投資は、急な出費やあらかじめ必要な時期が確定している教育資金の貯蓄には不向きと言えます。
投資のプロでもない一般人が、子供が大学に入学する15年後に値上がりしている株や投資信託を見極めるのは、かなり難しいですよね。
「お金が必要な時=儲かっている時とは限らない」というのが、投資は教育資金を貯めるのには不向きだと言われている理由です。
リスクを減らすには長期運用が基本
ただし、投資は長期運用するほど、損するリスクを軽減できると言われています。
なぜなら、短期間で見ると上がったり下がったり価格がコロコロと変動している投資商品も、10年・20年・30年という長い期間で見てみると、ゆるゆると右肩上がりになっているものが多いからです。
(というより、右肩上がりになっている商品を選ぶのが基本です☝️)
教育資金を貯めるという目的からすると、必ず必要になるお金になるべくリスクは背負いたくないので、基本的には長期運用がオススメ。
また長期運用は、複利効果を最大限に活かせるのもメリットです!
複利効果とは?
運用で得た利益を元本に加えて再投資することで、投資の利益も投資に回り、さらに利益を生むという効果のこと✏︎
毎年毎年、利益が元本に加わって投資が継続されるので、この複利効果は投資期間が長いほど効果を発揮します。
なので、教育資金の貯蓄に投資を考えている方は、早く始めれば始めるほど、リスクを軽減しつつ、良い運用成果を残せるでしょう。
リスクは最低限に!投資を上手く使って教育資金を貯めよう

投資を上手に使う方法①貯金や保険と併用する
先ほども述べたように、投資には教育資金を貯めるのに向かない一面もあります。
しかし、だからと言って貯金や学資保険だけで「お金を増やす」のには、限界があります💦
投資にもデメリットがあるように、他の貯蓄方法にもやっぱりデメリットはあるのです☝️
そこで・・・
オススメなのが、貯金や保険と「投資」を併用すること◎
貯蓄の方法を複数持っていることで、それぞれのデメリットをうまくカバーすることができます。
例えば、
✅子供手当は毎月現金で貯金
✅そのほか毎月1万円は子供のための投資に回す
という形にしておくと、すぐに必要なお金は貯金から補えるし、毎月1万円の投資分は10~20年後にかかるであろう大きな額の教育資金(大学入学など)に回すことができます。
投資を上手に使う方法②投資は5割以下に抑える
貯金・学資保険・投資の中でどうしても一番リスクが高くなってしまうのは、投資です。
なので、教育資金を作るという意味では、投資は全体の5割以下に留めておきましょう☝️
例えば、投資に対して少し不安がある方は、
毎月2万円を子供のために貯蓄する場合→(現金:投資=15000円:5000円)
と、まずは投資の割合を低く設定するのがオススメです。

投資への不安感がなくなってきたら、もう少し投資の割合を大きくしていくと貯蓄効率も上がるよ✨でも、まずは焦らずゆっくり☝️少額から始めていきましょう!
子供の教育資金を貯めるのにオススメの投資方法3選

子供の教育資金を貯めるのにオススメの投資①つみたてNISA
つみたてNISAとは、毎月一定額を投資信託に積み立てることで資産を増やす制度です。
投資信託とは?
私たちが投資したお金をひとつの大きな資金として、運用の専門家が株式や債券などに投資し運用する商品☝️その運用成果が、私たちに分配される仕組みになっています。
投資信託は、1つのファンドの中に色んな株式や債券が詰め込まれているので(バリューセットみたいなもの)、一つ持っているだけで分散投資ができるのが最大のメリット。
しかも運用はプロ任せなので、初心者でも簡単に始められるのがいいところです✨
ただし、その分、運用手数料が発生してしまいますが、最近はその手数料もどんどん安くなっています。
自分が許容できるリスクに応じて、投資するファンドを選びましょう☝️
子供の教育資金を貯めるのにオススメの投資②株の長期運用
株(=株式投資)とは、会社が資金集めのために発行している株式を購入し、その対価として株主総会の議決権や配当金・株主優待を受け取る権利を得るものです。
配当金や株主優待を受け取れるだけでなく、株式を安く買って高く売ることで利益を出すこともできます。
毎年の配当金や株主優待を換算すると、銀行に預けておくよりもはるかに良い利回りが期待できます。
⚠️一方、買った時よりも株価が下がり損をしてしまうリスクもあるので要注意です。
しかし、このリスクは長期で運用することによって軽減できるので、お子さんがまだ小さく教育資金が必要になるのは、10年・15年後という方にはオススメの投資方法です。
株式投資で教育資金を作ろうと考えている方は、リスク分散のため業種の違う株式を複数購入することをオススメします。
さらに2024年から新しくなったNISA制度では、つみたてNISAを利用していても、併用して非課税枠を使うことができるようになったので、よりオススメになりました☝️
ジュニアNISA(現在は廃止されています)
ジュニアNISAとは、日本に住む未成年(0~17歳)の子供のみが利用できる資産形成のための非課税制度です。
以下に特徴をまとめてみました。
- 最長5年間投資可能(廃止が決定しているので今からだと2年が最長)
- 年間80万円分は非課税
- 国内外株式、投資信託、EFT、IPO銘柄まで取引可能
- 5年後もロールオーバーでそのまま成人まで非課税(追加投資は不可)
- いつでも引き出せる(改正ポイント)
このようにみると、良いことだらけのジュニアNISAですが、口座開設者の数は伸び悩みついに来年の2023年で廃止が決定してしまいました。
なぜ人気が出なかったのかというと、当初このジュニアNISAは18歳まで引き出しができず、引き出した場合は遡って課税されるという設定だったからです。

子供の教育資金のために積立を始めるのに、18歳まで引き出せないなんて話にならんて。
ですが、皮肉なことに廃止が決まったと同時にこの部分が改正され、
- いつでも引き出しOK
- それまでの非課税分もそのまま
となったのです。
ここのデメリットが消えた途端、利用者が倍増したそうですが、残念ながらこちらの制度は終了してしまいました💦
【注意】子供の教育資金を貯めるのに向かない投資方法とは?

iDeCo(個人年金拠出制度)
iDeCoとは、皆さんも知っての通り年金制度の一つです。
原則60歳に到達するまで、掛け金と運用益を受給することは出来ませんので、教育資金を作ることには不向きです。
ただし、国民年金や厚生年金にプラスの老後の資金を確保しておくことで、iDeCoの掛け金以外は、安心して現状の生活費や教育費に充てることができるという点で、間接的に教育資金の貯蓄を手助けすることは出来ます。
教育資金の貯蓄に向かない理由
- そもそも利用目的が違う
- 原則60歳に達するまで受給できない
FXや先物取引などリスクの高いもの
FXや先物取引、ビットコインなどリスクの高いものは教育資金の貯蓄には向いていません。
ハイリスクなものに手を出してまで教育資金を貯めなくても、奨学金制度や子供自身にバイトで稼いでもらうこともできるので、全額を貯める必要はありません。
子供の教育資金を作るのに、大損を出してしまっては元も子もありませんよね。
こういったリスクの高い投資は、必ず余裕資金でしっかりと勉強をした上で始めましょう。
教育資金の貯蓄に向かない理由
- 教育資金を貯めるにはリスクが高すぎる
まとめ〜投資初心者にも分かりやすく〜
教育資金の貯蓄に向いているもの
- NISA枠を利用した株式投資→長期運用するほどリスク減
- つみたてNISA→プロが運用する初心者にオススメ
教育資金の貯蓄に向かないもの
- iDeCo→老後の年金制度で60歳まで受給できないのでNG
- FXや先物取引、ビットコイン→リスクが高いので教育資金作りには不向き
本ブログでは、「初心者・主婦・ママさん」に向けたコツコツ投資について発信しているので、良かったら他の記事も読んでみてください✨

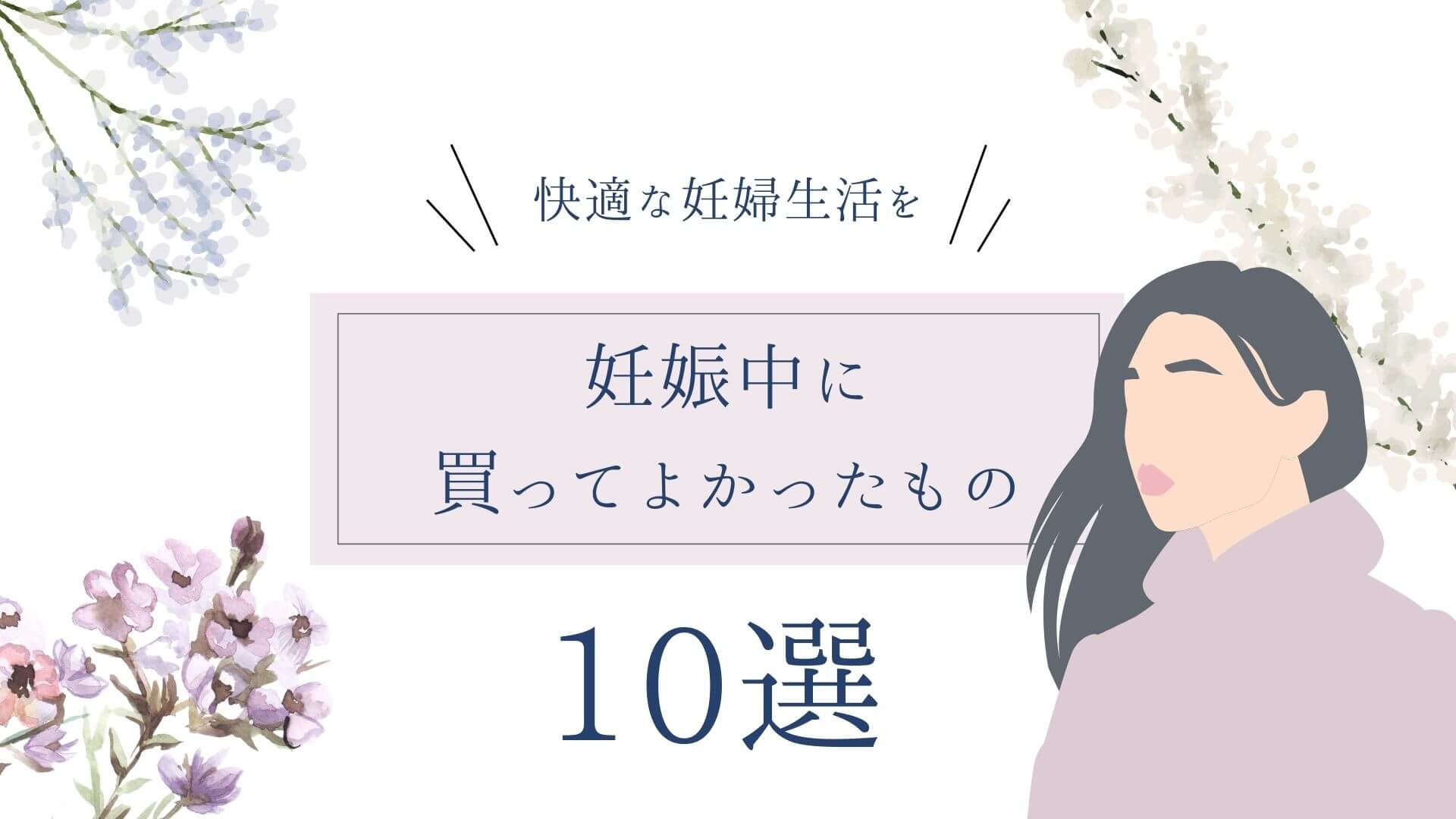
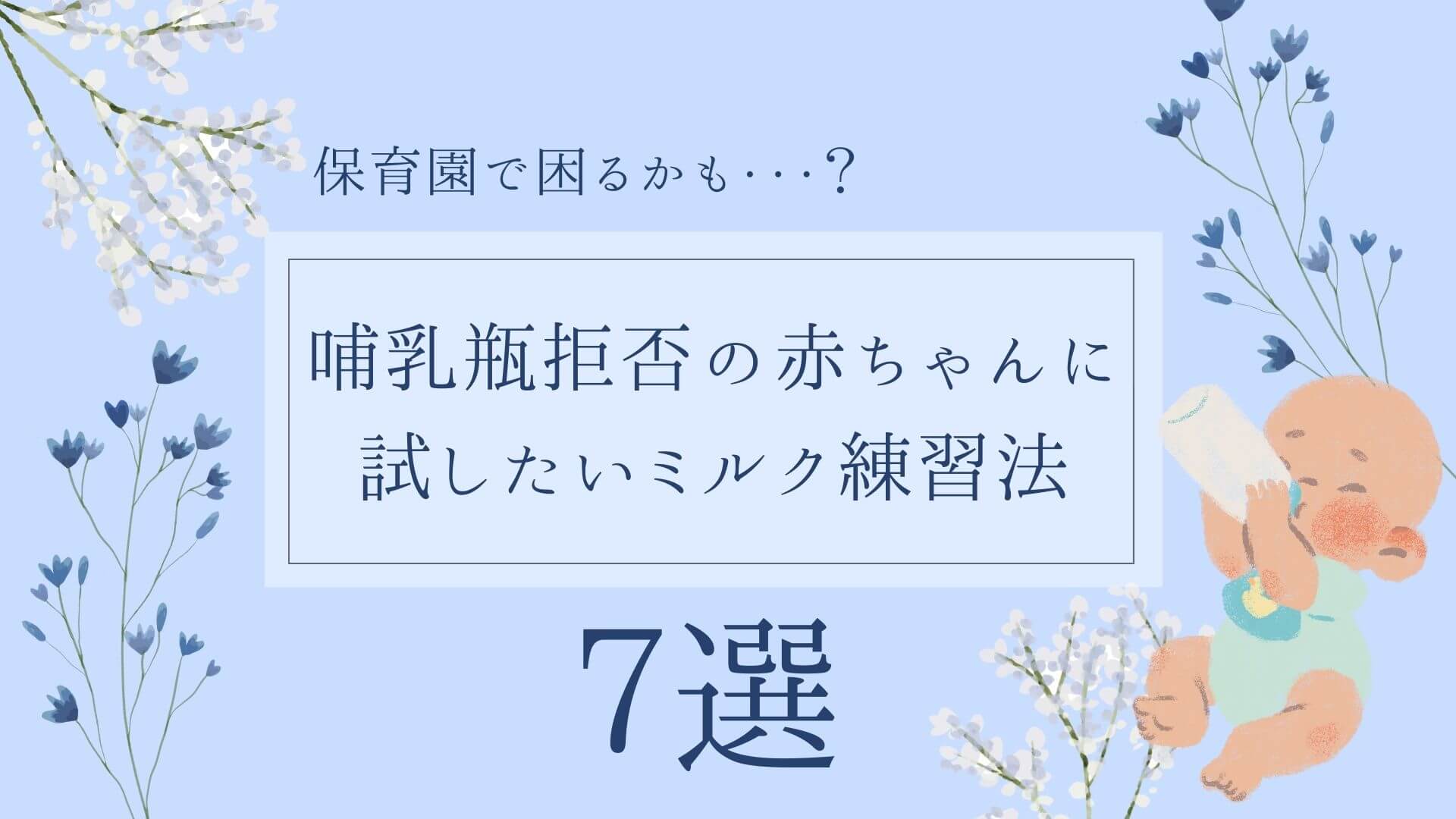
コメント