出産直後のママは・・・
赤ちゃんが産まれてすぐは、初めての経験ばかりで余裕のないママ。
体もかなり疲労しています💦(出産後のママの体へのダメージは交通事故に遭った時と同じとも言われています)

出産で体はボロボロなのに2~3時間ごとに起きて母乳を与えなくてはならないし、寝不足で出産後の手続きまで頭が回らないわ。
そこで、パパの出番です☝️
しっかり予習・準備をして、産後のママをサポートしましょう。
今回は分かりやすく産まれたらすぐに手続きをしないといけないものから、少し時間に余裕があるものまで順番にご紹介します!
産まれたらすぐに:お急ぎ度★★★

出生届
出生届は赤ちゃんの戸籍を作るためのとても大事な書類です。
提出は義務ですので、忘れずに必ず提出して下さい。
「出生届を提出していない=存在しない子」として扱われるので、赤ちゃんの健康保険証も作れず、予防接種や検診の案内も届きません。
- 提出期限:出産日を含め14日以内
- 提出場所:赤ちゃんの出生地・父又は母の本籍地・父又は母の所在地のいずれかの役所
《必要書類》
- 出生届(役所又は出産した産院で取得)
- 出生証明書(産後に出産した産院で取得)
- 届出人の身分証明書及び印鑑
- 母子手帳
児童手当金の申請
児童手当金とは、0歳から中学校卒業までの児童を養育している人に支給される手当金です。
児童手当金は申請をしなければ、受取ることが出来ないので忘れずに手続きを行いましょう!
◎3歳未満→月額15,000円
◎3歳以上~中学卒業→月額10,000円
※ 手当金の支給月は6月・10月・2月。前月までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
- 提出期限:出生日の翌日から15日以内
- 提出場所:現住所の役所
《必要書類》
- 児童手当認定請求書(各役所HPでダウンロード可能)
- 請求者名義の銀行口座
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の身分証明書及び印鑑
- 請求者の個人番号カード又は通知カード
※15日を過ぎてしまった場合でも申請は可能ですが、支給開始月と金額で損をしてしまう場合があるので、期限を守って手続きをしましょう。
現住所の役所への提出となるので、里帰り出産の方は予めパパに手続きを頼んでおきましょう!
パパも一緒に里帰りする場合は、郵送で対応できます。
赤ちゃんの健康保険加入
赤ちゃんの医療費助成を受けるのに必要な健康保険証。
一般的に、両親どちらかの年収が高い方の扶養として加入します。
- 提出期限:出生後すみやかに
- 提出場所:社会保険なら勤務先の管轄部署、国民健康保険なら居住地の役所
《必要書類》国民健康保険の場合
- 届出人の身分証明書及び印鑑
- 届出人の国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳
※社会保険の方は勤務先にご確認下さい。
手続きが遅れてしまうと・・・?
万が一保険証が届く前に病院を受診することがあった時、 病院によっては後日保険証を提示すればよいとして保険を適用してくれる所もありますが、医療費は基本的に自己負担になります。
ちなみに赤ちゃんの2週間・一ヶ月健診などはそもそも保険適用外なので保険証は必須ではありません。

でも、健診とあわせて治療をしたり、薬を処方してもらったりする場合もあるから、なるべく早く手続きを済ませておかなきゃね!
出来るだけ速やかに:お急ぎ度☆★★

子供の医療費助成の申請
子供の医療費助成 (乳幼児医療費助成制度) とは、子供が医療機関で治療や診察を受けた費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度です。
対象となる年齢や助成金額は居住地によって異なりますので、お住いの自治体HPをチェックしておきましょう✅
- 提出期限:子供の健康保険証が届いたらすみやかに
- 提出場所:各自治体の担当窓口
《提出書類》※東京都目黒区の場合
- 乳幼児・子ども医療証交付申請書
- 届出人の身分証明書
- 子供の健康保険証(後日提出可)
目黒区の場合、出生日から3か月以内の申請・健康保険証は後日提出OKですが、各自治体によって規定が異なりますので、事前に確認して下さい。
出生通知書
出生通知書とは出生届とは別物で、各自治体に送付するものです。
提出期限や受けられるサービスは各自治体によって異なるので、確認しておきましょう。
《 主なサービス 》
- 保健師または助産師が無料でお宅を訪問し、赤ちゃんの体重測定、入浴方法指導、育児相談などを行う
- 記念品や贈答品が貰える
提出は必須ではありませんが、初めての育児をするママさんは提出しておいた方が色々と相談やサービスを受けられて安心との声も多いです!
ひと段落したら:お急ぎ度☆☆★

里帰り出産時の助成金払戻請求
里帰り出産等で、所有している妊婦健康診査受診票が使えない地域の医療機関で受診をした場合、自費で支払った医療費の助成金額部分の払い戻しを行う制度。
妊婦検診以外も、 妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検査、新生児聴覚検査の費用を自費で支払った場合も払い戻し可。
参考:東京都目黒区の場合
- 提出期限:分娩日から1年以内
- 提出場所:区役所保健予防課又は最寄りの保健センター
《提出書類》
- 里帰り等妊婦健康診査費及び新生児聴覚検査費助成申請書(自治体HPでダウンロード可能)
- 請求書(自治体HPでダウンロード可能)
- 領収書(原本)
- 母子健康手帳
- 未使用の受診票
- 印鑑及び振込先の銀行口座
こちらも各自治体によって助成金額・期限が異なりますので自治体HPをチェックしましょう✅
出産育児一時金
出産育児一時金とは、保険適応外である出産費用の助成として、加入する健康保険組合から受け取れる一律42万円の補助金のことです。
- 提出期限:利用する受取方法によって異なる
- 提出場所:病院又は各健康保険組合の担当窓口
①直接支払制度
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われるので、退院時の支払いは42万円が差し引かれた残りの分だけ。
出産費用が42万円未満であった場合は、後日申請することで差額を受け取ることができます。
入院時までに病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入するだけで他に手続きは不要!
②受取代理制度
加入の健康保険組合に 「受取代理制度利用申請書」 を提出することで「直接支払制度」と同じように組合から医療機関に支払われます。
- 提出期限:出産予定日の2ヵ月前以降
- 提出場所:加入の健康保険組合
③産後申請
出産費用を全額自己負担し、産後に加入の健康保険組合へ申請し、払い戻しを受ける方法です。
- 提出期限:出産日の翌日から2年間
- 提出場所:加入の健康保険組合

ほとんどの医療機関で「直接支払制度」を採用しているので、事前に病院でこの方法を選ぶのがオススメよ✨
高額医療費制度
高額医療費制度とは、ひと月にかかった医療費の合計金額が高額になり、一定金額(自己負担限度額) を超えた場合、その超えた部分が高額療養費として戻ってくる制度です。
基本的に妊娠・出産は病気ではないので保険適用外となりますが、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合には適用されます。
- 提出期限:診察日の翌月から2年間
- 提出場所:健康保険組合の担当窓口
《提出書類》
- 加入健康保険組合に問い合わせ要
会社員で産休中のママはこちらの手続きも!

出産手当金の請求
出産手当金とは、産休中に加入の健康保険組合からお給料代わりに支給される手当金です。
- 支給対象期間:出産前42日間+出産後56日間=計98日分
- 支給額:月給の3分の2程度
- 提出期限:産後57日目以降~
- 提出場所:勤務先
提出期限・提出書類については勤務先によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
育休に関する手続き
産休が終わったら次は育休に入ります。
- 支払対象期間:産休終了の翌日から
- 支給額:1年間育休を取得する場合、最初の半年が67%、後半の半年が50%程度が目安
- 提出期限:育休開始から4ヶ月以内
- 提出場所:勤務先
提出期限・提出書類については勤務先によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ:産後はパパのサポートが必須
産後は余裕のないママに変わってパパのサポートが必須となります!
産前にしっかりと予習・準備をしておきましょう。
特にお急ぎ度★★★はパパが積極的に動くようにしましょう。
パパが事前に調べて予習しておいてくれると、ママも安心して出産に臨めると思います♪

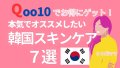

コメント